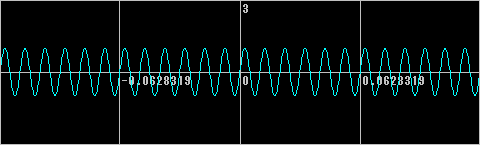 600Hzの音波を表す曲線の式を y = sin(600x) と仮定します。
600Hzの音波を表す曲線の式を y = sin(600x) と仮定します。差音というものを初めて聞きましたのでググってみましたらWikipediaに、「二つの音の周波数の差から生じるものには他にうなりがある。うなりは周波数の差と同じ周期で音の強弱を生じる現象で、差音とは異なる。 周波数の差が大きいものを差音、小さいものをうなりと呼ぶ。その境界は明確ではない。」とありましたので、これはおそらくうなりが溶けていったときの音だろうと推察できます。2-2-1-3 うなり の項で、f1 = 10、f2 = 9.5 のときのうなりについて説明し、その後 f2 が小さくなっていく(f1 との差が大きくなっていく)につれて、うなりが溶けていく、不明瞭になっていく、と説明しました。この不明瞭になった音が差音だと思います。
2-2-1-3 うなり において数式を用いて説明しなかったのが悪かったのですが、数式でうなりを考えるとはっきり分かります。
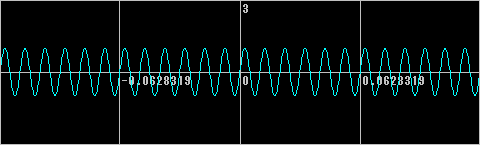 600Hzの音波を表す曲線の式を y = sin(600x) と仮定します。
600Hzの音波を表す曲線の式を y = sin(600x) と仮定します。
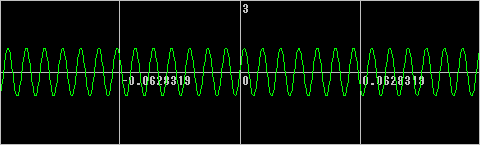 もう一つ同時に発する 660Hzの音波の式を y = sin(660x) と仮定します。
もう一つ同時に発する 660Hzの音波の式を y = sin(660x) と仮定します。
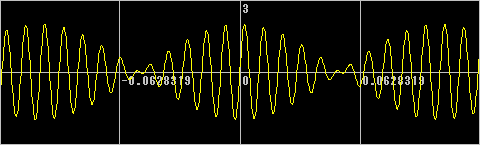 すると左図のようなうなりが現れます。うなりは2つの音波を重ね合わせの原理によって足し合わせたものだから、その式は y = sin(600x) + sin(660x) です。
すると左図のようなうなりが現れます。うなりは2つの音波を重ね合わせの原理によって足し合わせたものだから、その式は y = sin(600x) + sin(660x) です。
ここで三角関数の和積の公式 sinx + siny = 2sin{(x + y)/2} cos{(x - y)/2} を用います。
y = sin(600x) + sin(660x)
= sin[{(600+660)/2}x] cos[{(600-660)/2}x] cos(-30x) = cos(30x) なので
= 2sin(630x )cos(30x )
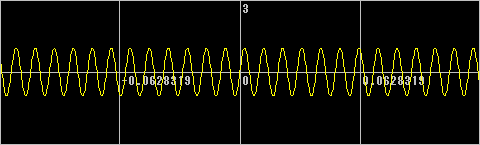 左図が y = sin(630x) の波です。
左図が y = sin(630x) の波です。
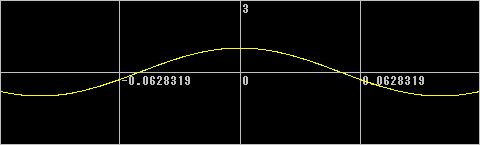 左図が y = cos(30x) の波です。
左図が y = cos(30x) の波です。
この2つを掛け合わせたものが上のうなりの波ということになります。そしてこのうちの cos(30x) がうなりで、sin(630x) が Shinoさんがおっしゃる平均値の音だと思います。y = 2sin(630x )cos(30x ) の右辺先頭の 2 に関してはy軸方向に伸ばすというだけのことで意味はないです。
ここで訂正がありまして、cos(30x) がうなり、といいましたがこれは間違いです。
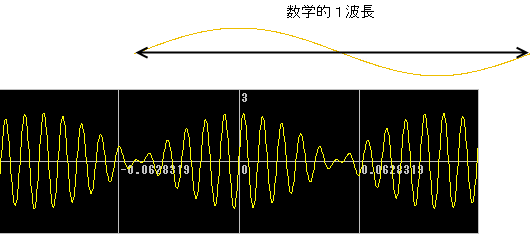 数学的な 1波長は左図のような部分のことであり、この部分が 30x を表します。
数学的な 1波長は左図のような部分のことであり、この部分が 30x を表します。
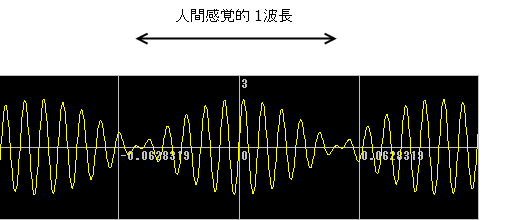 しかし人間が耳で聞く場合には左図のような部分を 1波長と感じるはずです。実際この波長がうなりの波長と定義されています。となると 30x というのは不適切で、30x * 2 としなければなりません。
しかし人間が耳で聞く場合には左図のような部分を 1波長と感じるはずです。実際この波長がうなりの波長と定義されています。となると 30x というのは不適切で、30x * 2 としなければなりません。
上の和積の公式を用いた計算のところで
cos[{(600-660)/2}x]
としたところは
cos[{(600-660)/2}*2*x]
としなければなりません。つまり
cos[(600-660)x]
です。
そしてまさに、600 - 660 = -60 の 60 がうなりの周波数です。30ではないのです。
次に2つの音波の周波数の差が大きい場合のうなりをみてみますと(3つの波を重ねて表示します)
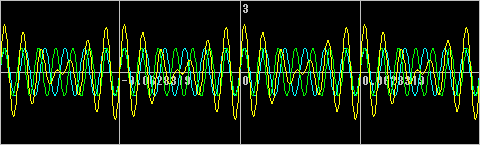 600Hz と 700Hz。うなりは 100Hz.。
600Hz と 700Hz。うなりは 100Hz.。
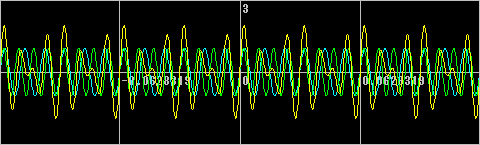 600Hz と 800Hz。うなりは 200Hz。
600Hz と 800Hz。うなりは 200Hz。
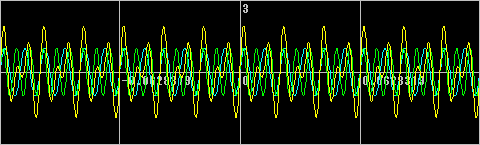 600Hz と 900Hz。うなりは 300Hz。・・・ですが、左図のような波形(黄色の波形)の音をうなりと感じるでしょうか。ここまでくるとうなりとは感じないので、差音と呼ぶことにしたのだと思います。
600Hz と 900Hz。うなりは 300Hz。・・・ですが、左図のような波形(黄色の波形)の音をうなりと感じるでしょうか。ここまでくるとうなりとは感じないので、差音と呼ぶことにしたのだと思います。
(2011/08/08 追記) 実際にうなりと感じる周波数は 2Hz 程度のようです。「うなりは 100Hz 」 「うなりは 200Hz」 と書いてしまいましたが、それくらいの周波数ではうなりと呼ばず差音と呼ぶのが適当かもしれません。ますださんという方から教えていただきました。
(2012/01/18 追記) このページの差音という言葉は使い方を間違えてるかもしれません。ふぇむさんという方に教えていただきました。詳しくは "ご感想"掲示板 での差音についての議論をお読みください。(2012/02/02 追記)特に"ご感想"掲示板のNo.548〜No.552にふぇむさんの考えがわかりやすくまとまっていますのでお読みください。(2012/02/07 追記)下の結合音についての記述も不正確です。"ご感想"掲示板のNo.593に詳しい解説がありますのでお読みください。
差音について調べているときに結合音という言葉がよく出てきたのですが、これについても少し説明しますと、
楽器というものは 600Hzの音を出したつもりでも、必ず 1200Hz、1800Hzなどの倍音、3倍音が出てしまします。(2-2-2-1 弦の振動 参照)。700Hzの音を出せば同時に 1400Hz、2100Hzの音も出てしまいます。それらの音の組み合わせによって様々な結合音が作られるのだと思います。1200Hz、1800Hzの音を出さずに 600Hzの音だけを出すとなるとそれは人工的な電子音でしか実現できません。